企業経営&IT戦略レポート
ITスタッフ戦略の新たなるビジョン
情報提供:株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン
オープン・テクノロジーの急速な台頭と、ITの加速度的な進化、さらにはアウトソーシングの活発化など、ここ10年足らずの間に、企業のIT組織を取り巻く環境は大きく変化している。そうした変化に対応すべく、すでに多くの企業が、自社で保有すべきITスタッフ像を再考し、組織戦略の立て直しを試みているはずだ。その際、最大の問題となるのが、IT組織を支える「コアの人材」をいかに確保し、育成していくかという問題である。以下、それらの問題の解決に向けた手法を、IT組織の現状や課題を踏まえながら導き出す。
変化を強いるもの
企業内IT組織(以下、IT部門)に役割の変化、あるいは質的な変化を強いている事象の1つは、企業ITそのものの変化にほかならない。
例えば、旧来の企業ITは、メインフレームを中心に築かれており、それを構成する技術や製品は、特定のメインフレーム・メーカーが提供するものに限定されていた。そのため、ユーザー企業のIT部門は、メインフレーム・メーカーが推奨する技術/製品だけを用いていれば、それでよかった。
ところが、1990年代後半からシステムのオープン化が急速に進み、さまざまな新技術、製品が矢継ぎ早に登場してくるようになった。その結果、企業のIT部門は、多数の選択肢の中から自らの判断で自社のニーズに合致したものを選定し、かつ、それらを組み合せてシステムを構築していくという、「自己責任」を負わねばならなくなったのである。
そうした“重荷”に加えて、今日のIT部門には、「ビジネス要求への迅速な対応」や「高度化を続ける新技術の導入」、さらには「コストの削減」という厳しい要求まで突き付けられている。言うまでもなく、1ユーザー企業のIT部門が、これらの要求をすべて満たしていくのは非常に困難である。
そこで浮上してきたのが、IT業務を外部にアウトソース(委託)するという選択肢であり、ここ数年来、ITアウトソーシングを採用する動きが、国内外のユーザー企業の間で活発化してきている。
実際、大半のユーザー企業にとって、ITはビジネス戦略上重要なインフラではあるが、それが提供するサービスや、その運用/管理といった業務は、決して企業のコア・コンピタンスではない。となれば、アウトソーシングによって、質の高いITサービスが安価に入手できれば、そのほうが合理的であると言える。
また、上でも触れたとおり、高度化を続けるITの導入や管理、活用を、ユーザー企業が単独で行っていくのにも限界がある。アウトソーシングは、そうした問題を解決する手段としても有効なのだ。
技術の空洞化を防ぐ
以上のような理由から、現在、日本のCIOやIT部門長の多くが、アウトソーシングの合理性を認めている。
しかし、その反面、システムの開発や運用を外部にすべて移管してしまうことに強い懸念を示す向きも少なくない。なぜならば、IT業務のアウトソーシングは、IT部門における「技術の空洞化」につながるおそれがあるからである。
例えば、ここに、システムの開発から運用までの一切を外部にアウトソースしている企業があるとしよう。こうした企業の場合、IT部門の若手社員は、開発や運用の経験を一切踏まぬままに、中堅のスタッフ(マネジャー・クラスのスタッフ)となり、ITベンダー側(アウトソーサー側)が提案してくる技術やプロセスを評価し、管理する立場となる。しかし、そうしたITマネジャーが、その任務を十分にこなせるかと言えば、非常に厳しいと言わざるをえないだろう。
実際、システムの企画やITベンダーの管理機能だけを社内に残し、その他のIT業務をすべて外部に移管してしまうと、時がたつにつれてIT部門全体(つまり、ITマネジャーを含めた、すべてのスタッフ)の技術スキルは低下する。要するに、そのIT部門は、ITベンダーの提案を正確に評価する「目利き」の能力を失うわけだ。そして、最終的には、システムの企画、およびITベンダーの管理機能をも放棄せざるをえなくなるのである。
こうした「技術の空洞化」を防ぐには、ITベンダーの提案を技術とビジネスの両面から正しく評価できる能力を、社内で維持する必要がある。すなわち、IT部門と、そのスタッフに対して、そうしたスキルを身に付けさせる必要があるわけだ。
したがって、企業は、自社で保持すべきIT部門の「コアの人材」と「コアのスキル」をしっかりと見定め、それに沿った人材育成を計画的に進めなければならない。また、アウトソーシングを選択しなかった場合にも、上で述べた「企業ITの変化」を的確にとらえ、自社のIT部門が「自己責任」をまっとうしうるスキル、および能力を、そのスタッフに身に付けさせておく必要があるのである。
「兼務」の弊害
では、現実はどうなのだろうか。はたして、日本の企業は現在、これからのIT部門に必要な「コアの人材」と「コアのスキル」を明確にし、それに沿った人材育成を進めているのだろうか。
残念ながら、現時点で、それを実践している国内企業は少ない。そのことは、ITRが昨年12月に実施した「IT戦略アンケート」(回答企業:223社)にもはっきりと示されている。
同アンケートには、「自社情報システム機能の主要機能(コア・コンピタンス)を明確化していますか」との問いが含まれていた。それに対して、定義なり大まかな概要なりを文書化しているとした企業は、全体のわずか3分の1にすぎなかったのだ。しかも、全体の37%が「明確ではない」と答えたのである(図1)。
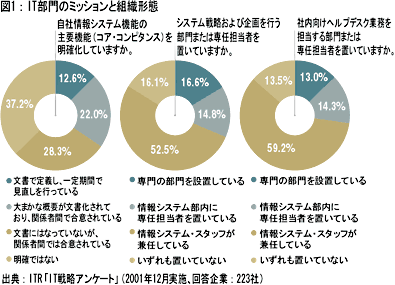
もちろん、IT部門のコア・コンピタンスを定義していなければ、そのスタッフが果たすべき責務や、持つべきスキルを明確にすることはできない。となれば、これからのIT部門を支える人材に対して、適切な教育を施すことも不可能となる。
また、国内企業のIT部門には、日本の組織特有の問題も存在する。それは、部門内のスタッフに、複数の業務を兼務させるケースが非常に多いことだ。
例えば、大半の日本企業では、ユーザー・サポートを担当するヘルプデスク業務や、システム戦略の立案といった特殊な業務についても、専任のスタッフを配置しておらず、それらを、他のIT業務に携わるIT部門のスタッフに兼務させている。また、開発担当のスタッフが、そのままシステムの運用を担当するのも、決して珍しいことではない。
言うまでもなく、IT部門が受け持つ個々の職務には、それぞれ異なるスキルが必要とされる。したがって、いくつかの職務を兼務するスタッフは、幅広い分野のスキルは得られるものの、特定分野に精通したスペシャリストにはなりえない。すなわち、スタッフによる複数業務の「兼務」を前提とするIT部門は、IT業務全般に対して一定のスキルを持つ「ゼネラリスト」しか育成できないわけだ。
よって、もし、自社のIT部門にスペシャリストを必要とするならば、「兼務」を前提とした業務体制を見直す必要があろう。そして、IT部門におけるスペシャリストとゼネラリストの比率をどの程度にすべきかを見定め、新たな体制作りと、教育プランの策定を進める必要があるのだ。
アウトソーシングと雇用不安
増大する社内のITニーズにこたえるため、コストやスキル、戦略上の理由から、アウトソーシングの拡大を計画しているCIOも多い。前出のCIO Magazine米国版の調査によると、過去1年間で社外のITサービス業者と臨時スタッフの利用を増やしたCIOは68%に上り、国内アウトソーシングを増やした企業が23%、海外のアウトソーシングを増やした企業が18%あった。また、今後1年間のうちに何らかのかたちで外部のITサービスの利用を増やす予定であると答えたCIOが全体の47%に達している。
「ギリギリの数のスタッフで切り盛りしながら、さらに10%の削減を迫られているようなCIOにとって、アウトソーシングは有効な選択肢だ。特に海外アウトソーシングを利用すれば、理論上30〜50%のコストを節約できると言われる」(モレロ氏)
一方で、アウトソーシングには、社内スタッフの不安を招くというマイナス面もある。今や有能なIT技術者でも、それ以外のスキル、例えばビジネス・プロセスやマネジメント・スキルがなければ職場での地位は危うい。だからこそ、ITスタッフらは、海外へのアウトソーシングによって自分の得意とする業務がなくなってしまうことを恐れる。
エレクトロニック・アーツのウェスト氏がこの問題に直面したのは、同社の開発業務の15%程度をインドの中堅ソフトウェア・ベンダー2社にアウトソーシングし始めたときだ。同氏は、社内開発者が不要になるのではないかという部下たちの不安を取り除き、アウトソーシングが“チャンス”であると考えてもらえるよう、組織体制を見直した。そして開発者の新規採用を中断する一方、スタッフにシステム解析の技術を学ばせ、市販ソフトウェアの評価作業を行うために事業部門の注文管理プロセスを理解させるなど、より戦略的なスキルを習得するよう奨励した。
「アウトソーシングは、社内スタッフの仕事を奪うものではなく、彼らがプロジェクト・マネジメントや分散型開発環境のマネジメント・スキルを身につける良い機会なのだ。新しい仕事に対する不安はあるだろうが、我々としては単に仕事を安く済ます手段としてではなく、IT部門全体として、より質の高い仕事を短期間でこなすための手段であるととらえている」(ウェスト氏)
育成計画の欠如
ここで再び、先の「IT戦略アンケート」に話を戻そう。前述したとおり、この調査によって、日本企業の多くがIT部門のコア・コンピタンスを定義していないことが判明した。これは、彼らがITスタッフの育成計画をきちんと立てていないことを示すものだが、そのことは、同アンケートの他の調査項目によって、より明らかになった。
例えば、同アンケートの「情報システム要員のキャリア・パスおよびスキル育成計画は存在しますか」という問いに対して、回答者の35%が「部門長の裁量に任されている」と答え、36%が「育成計画はない」としている。つまり、人材育成計画を明確にしていない企業が、全体の実に7割を超えているわけだ(図2)。
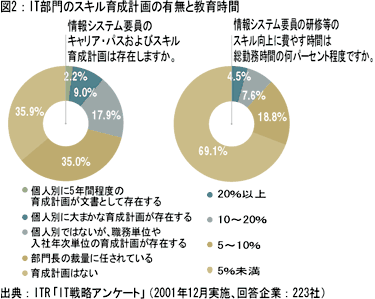
しかも、個人別の育成計画を持っている企業は、全体の12%にも満たなかったのである。加えて、「情報システム要員の研修等のスキル向上に費やす時間は総勤務時間の何パーセント程度ですか」という質問に対しては、約7割の企業が「5%未満」と回答している。
周知のとおり、ITの技術トレンドは著しく変化している。そうした中で、ITスタッフに与えられている技術研修の時間が、「総勤務時間の5%」というのは、あまりにも少なすぎると言わざるをえない。
もちろん、IT部門の中には、ITスタッフの教育を進めたくとも、業務が多忙を極めているため、そのための時間が確保できないというところも少なくないだろう。しかし、たとえそうであったとしても、ITスタッフにトレーニングの機会を与えていないことには変わりはないのだ。
いずれにせよ、人材育成の計画もなく、人材教育のための十分な時間も確保していない――これが大半の企業の現状である。これを極端に言いかえれば、「日本企業の大半のITスタッフは、自らのキャリアアップに向けた支援を会社からまったく受けていない」ということになる。
「技術の陳腐化」というリスク
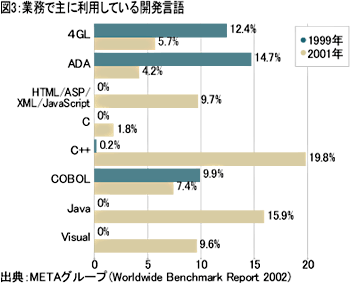
ITスタッフの育成にかかわる問題は、上記のような「社内体制の不備」という内的な問題だけではない。繰り返すようだが、企業ITのトレンドの変化、または、企業ITに求められる技術要件の変化も、ITスタッフの「コアのスキル」の見極めを困難にし、彼らの適切な育成計画を立てにくくしている要因の1つだ。
例えば、ここで図3をご覧いただきたい。これは、企業のIT部門で使用される開発言語の趨勢を、時系列的な分布として表したものである。ここからも分かるとおり、1999年の時点では、「4GL」や「ADA」が、IT部門における「主流」の開発言語であった。しかし、2001年においては、「HTML」「ASP(Active Server Pages)」「XML」「JavaScript」「C++」「Java」といった新たな開発言語が主流の言語として台頭し、上記2言語を非主流へと追いやっている。
このことは、IT領域における技術的な推移がいかに速く激しいかを示すのと同時に、1999年の時点で自社のITスタッフに対して行った4GLやADAの教育が、わずか2年後には意味をなさなくなったということを明らかにするものである。
また、それは、現時点で主流とされる技術、または製品についても同様に言えることである。
つまり、IT部門長が、仮に現在の主流言語であるC++やJavaをITスタッフに習得させたとしても、数年後には、それらの技術が陳腐化し、その教育に費やした労力や投資の一切が、回収されないまま無駄になるおそれがあるのである。
IT部門の役割と必須のスキル
ユーザー企業が、こうしたリスクを回避する1つの手段は、自社内(IT部門内)に技術スキルを保持しないようにすることだ。要するに、企業ITにおけるすべての技術的な課題の解決を、外部のITベンダーに一任してしまうという「アウトソーシングのモデル」が、ここでも再び浮上してくることになる。
ただし、すでに述べたとおり、この手法を取るとIT部門の「技術の空洞化」を招く。したがって、企業のCIOやIT部門長は、そうしたリスクと、「特定技術の衰退、陳腐化」というリスクのバランスを取りながら、どういったレベルの技術スキルをIT部門に保持させればよいのかを見定めなければならない。
その際に必要となるのが、自社のIT部門が果たすべき役割を明確にすることだ。そしてそれは、「2つの業際」に求められる役割を突き詰めていくことで明らかになる。
ここで言う「2つの業際」とは、「IT部門と外部のITベンダーとの業際」と、「IT部門と社内ユーザー部門の業際」を指している(図4)。
まず、外部ベンダーの業際においては、IT部門は、以下のような役割を演じなければならない。
(1)ベンダーが正確に理解できるRFP(提案要請書)を作成する
(2)ベンダーからの提案内容や見積もりを正しく評価する
ゆえに、IT部門には、以上の職務をまっとうしうる技術スキル(または能力)が最低限必要になる。
一方、社内ユーザーとの業際におけるIT部門の役割とは、以下のようなものである。
(3)ユーザー部門のニーズを把握し、要件定義として適切にまとめる
(4)ユーザーに受け入れられるサービス・レベルを正しく定義する
これら2つの役割をこなすには、それぞれ異なる能力が必要だ。つまり、上記(3)の職務を果たすには、「ITベンダーに対する社内ユーザーの代弁者」として機能する能力が求められる。これに対して、(2)の職務をこなすには、「社内ITコンサルタント」として機能しうる能力が必要とされるのである。
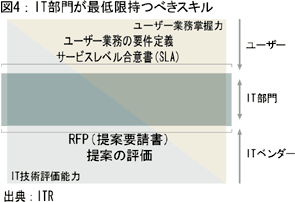
2つの「スペシャリスト」像
以上の観点から、IT部門に求められる能力、または技術スキルをとらえると、そのスタッフに必要とされるスキルや、育成の方向性がおのずと見えてこよう。
例えば、上述したIT部門の役割から考えた場合、IT部門が保有すべき「コアの人材」のあるべき姿は、大きく2つに大別することができる。そのうちの1つは、技術的な「目利き」ができる「ITアーキテクト(技術者、設計者)」であり、もう1つは、ユーザー業務を理解し、そのうえで経営の高度化を支援しうる「ITコンサルタント」だ(図5)。
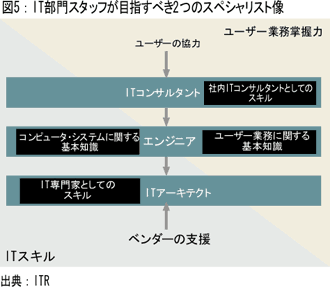
むろん、IT部門のスタッフならば、コンピュータ・システムやユーザー業務に関する基礎的な知識は、だれもが保持しているだろう。ただし、上記のようなスペシャリストの場合、それに加えて、より専門的な知識やスキルが必要になる。
よって、CIOやIT部門長は、部門内にITアーキテクトや社内ITコンサルタントをそれぞれ何人、または、どのような比率で配置していくかをあらかじめ定め、その計画に沿った人材育成の戦略を練っておく必要がある。
当然のことながら、ITアーキテクトと社内ITコンサルタントの人的な比率をどうするかは、企業によって異なるだろう。ただし、企業ITの領域では今後、アプリケーション・パッケージの利用や、アウトソーシングの利用がいっそう進展すると思われる。となれば、IT部門の軸足は、システムの「構築」および「運用」から、「活用」へと大きくシフトするはずだ。そう考えると、社内ITコンサルタントの数は、ITアーキテクトよりも多くなければならない。筆者の私見を述べさせてもらえば、ITアーキテクトと社内ITコンサルタントの比率は、3対7程度が妥当な線ではなかろうか。
いずれにせよ、IT部門に必要な「コアの人材」を明確にし、それぞれの人的リソースの配分を明確にしたならば、今度は、それに沿ったかたちで、ITスタッフのキャリア・パスを整備しなければならない。大抵の場合、IT部門に配属された“新人”は、まず初めにコンピュータ・システムやユーザー業務に関する基礎知識を身に付ける。その後、3年間ないし5年間は、特定の分野に偏らず、広範な業務の経験を積むのがよいだろう。
問題はそのあとだ。その後に、明確なキャリア・パスが何もなければ、それは、ITスタッフにとって不幸なことであり、彼らのモチベーションも上がらない。広範な業務知識を身に付けた後には、ITアーキテクトになるか、社内ITコンサルタントになるかの道筋を用意しておくべきだろう。また、それが、IT部門における理想的なキャリア・パスのあり方だとも言えるのである(図6)。
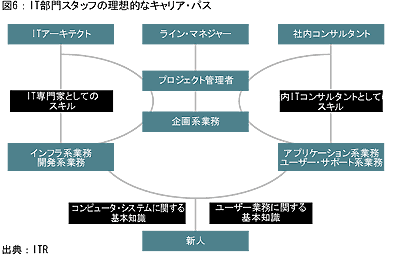
さらに言えば、ITスタッフのキャリア・パスの1つとして、IT部門長などのライン・マネジャーへの道筋を用意しておくことも忘れてはならない。
ITアーキテクトの育成法
では、企業は、上記の2タイプのスペシャリストを目指すスタッフに対して、どのような教育を施すべきなのだろうか。
まず、ITアーキテクトの育成計画には、ITの技術的な研修はもちろんのこと、各種技術認定資格の取得といった項目を盛り込む必要がある。ただし、一口にITと言っても、その領域は多岐にわたり、個々人がすべての技術に関する高度なスキルを保持するのは難しい。
したがって、企業はITアーキテクトにどのような技術スキルを、いかなるかたちで保持させるかも見定めておく必要がある。要は、「幅広い技術知識は有しているものの、特に秀でたスキルはないITアーキテクト」を求めるのか、それとも「苦手な技術分野はあるものの、特定の技術に関しては卓越した知識と技能を有するITアーキテクト」を求めるのか、という問題である(図7)。
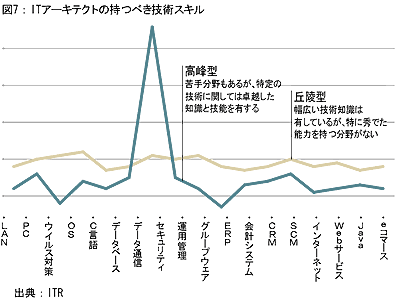
もし、ITアーキテクトになるべき人材がIT部門内に非常に限られた数しか存在しないというのであれば、1人のITアーキテクトに広範な技術知識を保持させておく必要があるだろう。
しかしながら、例えば、「高い峰の上に立つと、周囲の景色がよく見通せる」ように、特定の技術に精通したITプロフェッショナルは、大抵の場合、他の技術についても「見る目」を持っている。したがって、少なくとも、IT部門が組織として非常に重要であると見なすコアの技術に関しては、それに精通したITアーキテクトを育成することが望ましい。
求められるコミュニケーション能力
一方、社内ITコンサルタントには、ITアーキテクトとは異なるスキルが必要とされる。よって当然、それに見合った育成の計画を立てなければならない。
先に触れたとおり、社内ITコンサルタントとは、社内の業務改革や経営の高度化を支援する人材のことだ。つまり、社内ITコンサルタントは、そうした課題をITの活用によって解決しようとするプロセスにおいて、主導的な役割を担うことになる。
今日の企業は、ビジネス環境の変化に合わせて、絶えず変革を繰り返さなければならない。そうした中で、企業が自社の主体性を維持しながら、時代やニーズの変化に柔軟に対応していくには、企業全体を見渡し、その改革の作業を牽引していけるスキルなり、人材なりを確保することが重要である。まさしくそれが、社内ITコンサルタントを育成し、社内に保有するということなのである。
現在、企業の多くは、案件ごとにプロジェクト・チームを組織し、それによって社内の業務改革や経営の高度化を図るという手法を取っている。しかし、これからは、社内に専任のコンサルティング要員を保持し、その人員にすべてのプロジェクトを担当させるという体制が敷かれるだろう。
実際、ここ最近になって、経営企画部門やIT部門から“精鋭”をより抜き、社内的なコンサルティング・チーム(もしくは部門)を組織するというケースが、日本でも見られ始めている。
むろん、その背後には、「外部のコンサルティング会社に支払う料金を削りたい」という消極的な理由もあるだろう。しかし、コンサルティング業務に特化した専任者を社内に抱えることのメリットは、それだけにとどまらない。外部のコンサルティング会社と協力し、社内改革を進める際にも、社内コンサルタントがいたほうが、その成果が「絵にかいたモチ」で終わる危険性がはるかに低くなるのだ。
また、小規模な案件であれば、社内のコンサルティング部門だけで十分に対応できるだろう。つまり、彼らが主導的な立場でプロジェクトに参加し、かつ、外部コンサルタントから過去に吸収したノウハウなり、業務を通じて得たスキルなりを縦横に駆使していけば、ユーザー企業は、自社の力だけでプロジェクトを遂行することが可能になるのだ。
そうしたコンサルティング部門を構成するITスタッフ、すなわち、社内ITコンサルタントに求められるスキルは、いくつかある。なかでも必須なのは、以下の3つだ。
●コミュニケーション・スキル
●プロジェクト管理能力
●コンサルティング・テクニック
また、これらに加えて、ITおよび自社業務に関する基本的な知識も身に付けておかなければならない(図8)。
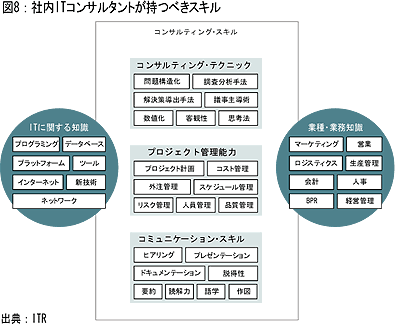
上に示した3つのスキルの中で、「コミュニケーション・スキル」は、ITコンサルタントにかぎらず、企業人すべてに共通して求められる基本的なビジネス・スキルである。ただし、コンサルティングという特殊な職務をこなすには、一般的なビジネス・スキルとしてのコミュニケーション・スキルを超えた、プロフェッショナルとしてのスキルが必要とされる。具体的には、「相手の話を論理的に再構築し、確認を取るスキル」や、「物事を単に人に伝えるだけではなく、相手を納得させる話術(テクニック)」などを身に付ける必要があるわけだ。
また、社内ITコンサルタントが活躍する場の多くは、プロジェクト案件である。したがって、「プロジェクト管理能力」も、社内ITコンサルタントにとって必須のスキルとなる。
さらに、コンサルティングを遂行するうえでは、調査や分析、課題整理、解決策の導出といったコンサルティング手法を駆使しなければならないケースも多い。ゆえに、社内ITコンサルタントは、そのためのノウハウ、換言すれば「コンサルティング・テクニック」も習得しておく必要があるのだ。
以上のようなスキルを、自社のITスタッフに吸収させるには、それ相応の専門教育が必要になる。また、社内ITコンサルタントへのキャリア・パスに、IT部門からユーザー部門への配置転換といった人事ローテーションを組み込むことも有益だろう。なぜならば、そうすることで、IT部門のスタッフは、現場での実務経験や業務知識を効率的に取得することができ、また、一定のコミュニケーション・スキルも身に付けることができるからだ。
さらに、これはITアーキテクトについても同様に言えることだが、社内ITコンサルタントなどのスペシャリストを育成する場合には、企画系の業務や、プロジェクト管理などの経験を積ませたほうがよい。そうすることで、スタッフは、より高度な専門性を身に付けることができるからである。
優れた人材を失う前に
これまで、ユーザー企業のIT部門は、総じて、ユーザー部門の「下請け組織」としての役割しか演じてこなかった。しかし今日では、ビジネス改革に対する高い意識を持ち、企業の変革の一翼を担う組織としての活躍が期待されている。
そうした中で、IT部門が改革のリーダーシップをとっていくためには、従来のITスタッフの枠組みとは一段違ったレベルにいるプロフェッショナル、すなわち、ITアーキテクトや社内ITコンサルタントを「コアの人材」として育成していくことが必要となるのである。
実のところ、企業のIT部門には、自社の全体像を把握する能力や、物事を構造的にとらえる能力に優れた人材が、他部門に比べてもたくさん存在するケースが多い。したがって、彼らの潜在能力を引き出す努力さえ惜しまなければ、優秀なITアーキテクトや社内ITコンサルタントの育成はそれほど困難な作業ではないはずである。逆に、それを怠り、優れた人材を組織の中に埋没させてしまえば、企業は、ITアウトソーシングの活性化や労働市場の流動化といった流れの中で、優秀な人材の多くを失うことになろう。
それを避ける意味でも、企業のCIO、またはIT部門長は、ITアーキテクト、そして社内ITコンサルタントといった「コアの人材」の育成に向けて動き始める必要があるのだ。


