企業経営&IT戦略レポート
ユーザー系情報システム会社は生き残れるか?
情報提供:株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン
日本特有の企業組織形態として、大手ユーザー企業のIT部門を分社化した情報システム子会社という存在がある。
そんなユーザー系情報システム会社の多くは、長らく親会社に依存するかたちで売上げを確保してきたが、ここにきて、親会社からのコスト面での圧力や市場競争力の相対的低下により、その業績が悪化してきている。
だが、親会社やグループ企業以外への営業(外販)強化で自主独立の道を選ぶにしても、グループ事業への貢献を深めるにしても、ユーザー系情報システム会社の抱える課題は根深く、前途は多難である。
本稿では、ユーザー系情報システム会社の悩みを分析し、今後それらの企業がとるべき方向性を探る。
システム子会社の“深い悩み”
ユーザー系情報システム会社は、ある時点まで、親会社やグループ企業における情報化の推進に歩調を合わせるかたちで人員を増強し、堅調に売上げを伸ばしてきた。そんな中で、一部の企業は早い段階からグループ外企業を対象とするいわゆる外販事業に目を向け、システム会社として自主独立することを目指してきたが、大半は親会社の“庇護”の下で経営を維持してきたというのが実情だろう。
しかし、近年、親会社側のIT予算の緊縮化傾向とともにコスト削減のプレッシャーが強まり、一方で目まぐるしい技術革新の中で自らの競争優位性を見いだしにくくなるなど、その経営はかつてない苦況に立たされている。
では、そうした企業の経営者らは、自社の課題をどのように認識しているのだろうか。それを知るべく、今年7月に開催された「第1回ユーザー系情報システム会社経営者フォーラム」(主催:ITR、協力:CIO Magazine)の参加者26人を対象に行ったアンケート調査「ユーザー系情報システム会社・悩み度チェックリスト」の結果を基にその実態を分析してみた。同調査では、20の質問に対して、それぞれ「まさに当てはまる」、「やや当てはまる」、「当てはまらない」から選択してもらい、回答に2、1、0ポイントの重みを付けて「悩み度」の平均値を求めた。
その結果、図1に示すとおり、「システム会社のコストや単価へのプレッシャーが以前より厳しくなった」が最も高い1.5ポイント、次いで「悪い意味で“身内感覚”から抜け出せず、あいまいな点が多い」が1.38ポイント、続いて「親会社への課金は、サービス対価というよりはコスト積み上げ方式である」(1.27)、「全体に間接部門意識が残っており、営業マインド・事業マインドが育たない」(1.27)、「得意技と呼べる秀でた技術分野を持てていない」(1.23)の順となり、これらが「悩みトップ5」であることが明らかになった。以下、5つの悩みについて、それぞれ掘り下げてみることとしよう。
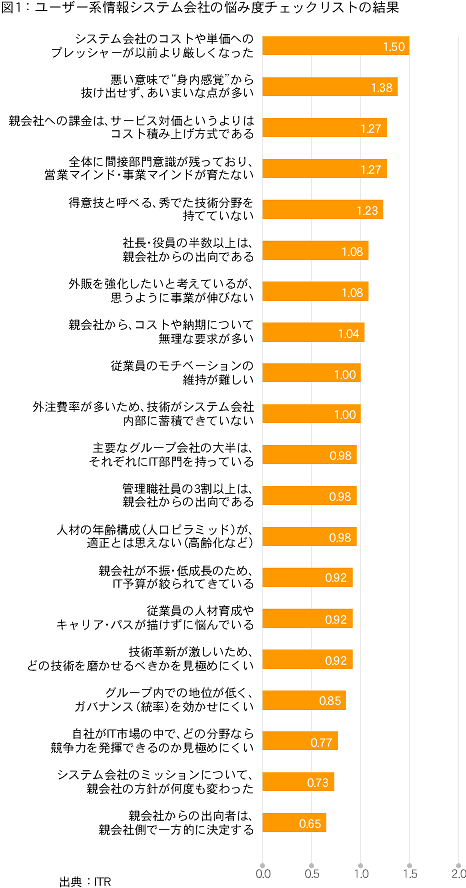
1.コスト切り下げの圧力
昨今の経済状況を反映して、コスト削減はシステム会社にとっても非常に大きな命題となっている。
もっとも、コスト削減圧力の厳しさという点では、ユーザー企業のIT部門も同様だ。CIO MagazineとITRが実施した「IT投資動向調査2003」においても、2003年のIT戦略での最重要項目として62%の企業が「コスト削減」を挙げており、「情報の活用度の向上」に次いで第2位となっている。このように企業における情報システム予算の緊縮化が進めば、情報システム会社への業務委託費に対してプレッシャーが強まるのは当然のことだと言える。
しかし、コストや単価へのプレッシャーにはもう1つ重要な原因があることを忘れてはならない。それは、コストや単価の算出根拠に対する説明責任(アカウンタビリティ)の問題である。これは、ユーザー系情報システム会社だけの問題ではなく、むしろIT業界全体の課題だが、現状では顧客に提示する価格やシステム・エンジニア単価に対して明確な算出根拠や基準を提示できるベンダーがほとんど存在しない。
ただし、一般のシステム会社は常に市場競争にさらされているため、サービスの価格が不当に高ければ顧客が離れていくことになる。ところが、情報システム子会社の場合、もともと自由競争が成り立っておらず、サービスの質や価格に対する顧客の不満がより蓄積されやすいと考えられる。
2.“身内感覚”の弊害
グループ内の情報システム会社の場合、互いに“身内感覚”があるため、契約などに際してあいまいな点が残りやすいという問題もしばしば指摘される。あいまいな点には、前述のコストや価格に関する説明責任も含まれるが、それ以外に、提供するサービス・レベル、契約内容、発注および受注責任、納期、要求仕様などさまざまなものが挙げられる。先の調査では、「親会社から、コストや納期について無理な要求が多い」という項目が第8位に挙げられているが、これも身内感覚が原因してのことだろう。
こうした意識は、組織や人間関係に起因していることも多いようだ。実際、調査では「社長・役員の半数以上は、親会社からの出向である」、「管理職社員の3割以上は、親会社からの出向である」がそれぞれ第6位と第12位に挙げられている。これは、親会社との間のパイプ作りという意味では有効かもしれないが、一方でそれがなれあいの原因となることにも注意しなければならない。そうした弊害を最小限に抑えるためには、親会社はシステム会社を1ベンダーと見なし、システム会社は親会社を1つの顧客と考えることが必要になってくる。
3.コスト積み上げ方式の価格設定
グループ企業内のサービス価格は、サービス対価ではなく、「100人の従業員、オフィス、システムを維持するためには50億円が必要だから50億円の委託費が欲しい」といったような“積み上げ式”の論理で決まることが多い。そもそもコスト算出基準やサービス・レベルがあいまいで、開発要件も十分に詰まっていないという状況では、適切なサービス対価を見積もること自体が無理な話だと言える。
特に、情報システム子会社の場合、要件変更による追加開発やシステム運用負荷の増大といったことがあっても、外部ベンダーのようにドライに追加コストを要求できないという問題がある。そのため、何らかのかたちで「提供した価値を正当に評価して課金する」ための仕組みを導入することが必要となろう。
4.間接部門意識の蔓延
独立した企業体とはいえ、外販をほとんど行っていないユーザー系情報システム会社の場合はコスト・センターと位置づけられることが多く、事業意識が欠落しがちである。外販を強化している企業であっても、総じて営業部門の社内における地位が低く、人員が少ないなど、営業が重視されていない傾向が目立つ。親会社からの出向社員が多いことも、その1つの要因となっていると考えられる。これでは厳しい市場競争にさらされているという危機意識も生まれにくい。
5.得意分野の欠如
外販を強化していくうえでは、「得意分野」となる技術やノウハウを継続的に打ち出せるかどうかが成功のカギを握っている。だが、ITの世界は技術革新が激しく、1つの技術分野における優位性が長年通用するとは限らないため、技術研修や研修投資の振り向け先を見極めにくいという問題がある。ただし、優位点は、JavaやXMLのような特定の技術分野である必要はない。むしろ、業務知識や業種知識、コンサルティング能力、プロジェクト管理スキルといった分野で優位に立つことが重要である。特に、ユーザーの業務に近い分野で力を発揮することで優位性を高めることができるはずだ。
以上の「悩みトップ5」から導かれる課題をまとめると、以下のようになる。
■説明責任
コストに対するプレッシャーが増大している中で、提供するサービスや人材の価値を明確に説明する手立てがない
提供するサービスのメニューや水準があいまいである
■意識改革
大手企業の傘下にあるため、概して間接部門との意識が強く、事業マインドや営業マインドが育っていない
“身内感覚”から抜け出せず、親会社・グループ会社への依存体質が根強い
■競争優位性
得意分野を持っていないため、外販を指向しても他社との差別化が図れない
自社のコンピタンスを明確に提示できず、親会社/グループ会社に対してもリーダーシップが発揮できない
これらを踏まえたうえで、前出の20問から成るチェックリストに対する回答に重みづけを施した集計結果を見てみよう。最大で40ポイントとなるが、30ポイント以上が14%、25ポイント以上30ポイント未満が15%、20ポイント以上25ポイント未満が42%と、ここまでで70%以上を占める(図2)。つまり、この20問のチェックリストは、多くの企業の悩みとかなりの程度まで一致していると言える。
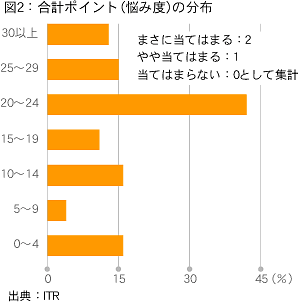
グループ企業の優位点
これまでユーザー系情報システム会社のネガティブな面ばかりを見てきたが、実際には、そうした会社の特性がビジネス遂行上、優位に傾く場合も少なくない。
まず、最大の優位点は、親会社やグループ会社といった安定した大口顧客を抱えていることである。コスト面での要請が厳しくなってきているとはいえ、自由競争にさらされるよりは、はるかに有利なポジションにあると言える。
また、そうした大口顧客が絶好の“実験場”になるというメリットも見逃せない。ERP(Enterprise Resource Planning)の導入や大規模なシステム再構築プロジェクトに参画できれば、システム会社として貴重な経験を積むことができるからだ。計画の初期段階から社内の動きを把握しやすいという点も、グループ企業ならではのアドバンテージである。
なかでも特筆すべき優位性は、親会社やグループ会社の属する業界事情や業務プロセスのあり方、組織形態などを通して、業界知識と業務知識が豊富に蓄積できるという点である。これは、同規模の独立系システム会社から見ればうらやましいかぎりの、きわめて恵まれた条件である。このような優位点をうまく生かせるかどうかが成否の分かれ目となろう。
さて、ここでもう1つ課題がある。それは、「二兎を追うものは一兎をも得ず」――言うまでもなく、グループ事業に対する貢献と外販強化の2つの戦略を両立させることは容易ではないということだ。
しかし、この2つの方向性は、本当にそのような二律背反の関係にあるのだろうか。外販も、結局のところは顧客企業の成功を支援することを目的としている。したがって、親会社やグループ会社を「顧客」ととらえることができれば、グループ企業向けサービスであっても、外販であっても、方向は同じだと考えるべきではなかろうか。
むしろ、適切な価格で、付加価値の高いサービスを提供し、顧客の課題解決や事業戦略推進を支援することができれば、グループ事業への貢献も外販の強化も同様に実現できるはずである。また、一般企業からサービスに対しての高い評価が得られれば、グループ企業に対しても説得力を持ってリーダーシップを発揮できるだろう。
「良循環」を築くために
以上述べてきたように、ユーザー系情報システム会社が“甘えの構造”から脱却し、真に意識改革を進めていくうえでは、自社の存在理由、行動原則、コンピタンス、サービス・メニュー(やること、やらないこと)を明確に定義することが求められる(図3)。
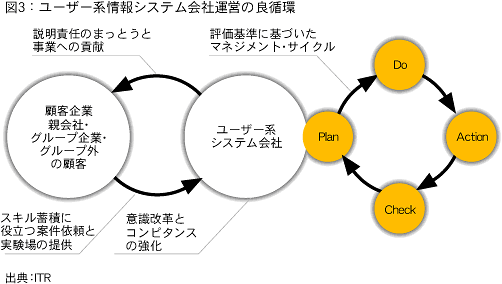
その際、顧客に対する説明責任をまっとうしながら、自社のコンピタンスを強化していくためには、まず「己を知る」ことから始める必要がある。
すなわち、コストや単価、技術者のスキル、市場におけるポジション、サービス・レベルなどさまざまな視点からの評価基準を定め、自社の実態を把握することが求められるのだ。
そのうえで、基準に基づいて目標を設定し、その達成度をモニタリングしながらマネジメント・サイクルを回していけば、自らの実行力を高めることができる。
情報システム子会社は、グループ企業にとって最も身近なITの専門家集団であり、一方でユーザー業務に対する理解の深さを大きな強みとしている。それゆえに、今後はグループ経営を前提とした業務改革やITガバナンスを主導する“グループ内コンサルタント”の役割を担う人材の育成がますます重要となろう。
親会社からの圧力やグループ内の地位の低さを嘆いていても始まらない。自己評価やサービス明確化など、できることから確実に実行し、一歩ずつ信頼を勝ち得ていく以外に道はないのである。


