企業経営&IT戦略レポート
“ここ”がいけない、ITアウトソーシング
情報提供:株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパン
日本で、ITアウトソーシング・サービスが提供されるようになってから、すでに10年以上がたった。この間、アウトソーサーたちは、それなりの数のアウトソーシング案件をこなし、その中で、「いかにもうけるか」という知恵を身につけてきた。だが、一方のユーザー企業はといえば、どうだろうか。固定的な関係を続けてきたことで、知識・経験の両面で後れを取り、その結果、アウトソーサーと不利な契約を結ばざるをえなくなってしまっているように感じられてしかたがない。本稿では、ユーザー企業が主導権を握って、アウトソーシング・コストの妥当性を厳しく問い、今後の激変するビジネス環境においても十分に効果を出せるようなアウトソーシングを実現するために、CIOが今、何をなすべきかについて考察する。
“丸投げ”が生む悲劇
今、多くの企業がITのアウトソーシングとコストの問題で頭を悩ませている。社内でまかなってきた業務を切り出し、それをアウトソーサーに任せることで、ITリソースの最適化とコストの削減ができるというアウトソーシングのメリットを、額面どおりに享受できているユーザー企業が思いのほか少ないのだ。
ITアウトソーシングのメリットが十分に得られない要因としては、さまざまなものが考えられるが、その第1は、やはりユーザーとアウトソーサーとのつきあい方そのものにあると言える。
日本企業はこれまで、ITインフラを運用するアウトソーサーを選定するに際して「過去のつきあい」を最重要視してきた。「開発を頼んだベンダーにそのまま運用も任せる」といった形態が多くの企業でとられているのもその証左であろう。
確かに、大規模なシステムを開発し、そのシステムを安全に運用するという段になれば、当該システムに対する豊富な知識を持ち、なおかつ勘どころを押さえている開発ベンダーが魅力的に映るのも理解できる。だが、国内でこれまでこうした“丸投げ”とも言えるアウトソーシングが行われ続けてきたのは、そうした理由からだけではない。あえて言えば、それを許したのは、過度にリスクを怖れるユーザー企業の姿勢そのものだと言えるのである。
仮にアウトソーサーを代えて、その結果サービス・レベルが低下すれば、CIOならびにIT部門の責任が真っ先に問われるのは明らかだ。その点、つきあいの深いベンダーに半永久的に業務を任せておけば、コミュニケーションも取りやすいし、安心感も得られる。つまり、日本の多くのユーザー企業は、こうした「安心」のために、アウトソーサーに多額の資金を投じていたとも言える。
しかもやっかいなことに、ユーザーがアウトソーサーを頼る最大の原因であるリスクへの恐怖心は、技術の進展につれて増すことはあっても減ることはない。そうした中で“丸投げ”を続けていけば、ユーザーとアウトソーサーとの間の知識/経験の差は日増しに拡大し、結果的にユーザーの統制力は大きく削がれることになってしまう。そうなってしまっては、アウトソーシングによってコストを削減することなど、もはや夢物語である。
当然ながら、一方のアウトソーサーにとっては、上述したようなユーザー企業の傾向は、願ってもない追い風である。一度契約してさえしまえば、よほどの失敗をしないかぎり、安定した収入が約束されるのだ。そこで、何とか最初の契約を取り付けようと、ありとあらゆる手段を講じることになる。
そもそもアウトソーサーは、あらゆる企業との間でハードな交渉を幾度となく乗り切ってきた強者である。契約更改などにおいても、さまざまなノウハウを蓄積しており、ユーザー企業の泣き所をピン・ポイントで突くことには長けている。そのようなアウトソーサーにしてみれば、経験の少ないユーザー企業との交渉を有利に運ぶことなど、赤子の手をひねる程度のことだ。
現に、契約更改の際に別のアウトソーサーへの乗り換えを検討していた日本企業が、交渉の過程でその計画を断念してしまうといったようなケースは枚挙にいとまがない。
ユーザ企業が何の戦略も持たず、丸腰で立ち向かうには、アウトソーサーは“強すぎる敵”なのである。
アウトソーサーの戦略を読む
ユーザー企業が、上述したような“アウトソーシング中毒”とも言える状況から脱するには、やはりアウトソーシングについての確固たる戦略を持つしか道はない。そして、それを実現するための第一歩は、当の相手であるアウトソーサー側の戦略をきちんと把握することではないだろうか。アウトソーサーの一般的な戦略を挙げれば、以下の4点になる。
■ “損して得とれ”
■ サービス内容はあいまいに
■ ユーザーに“得をした気分”を味わわせる
■ 売上げを減らすような提案はしない
アウトソーサーにとっては、すべてのビジネスは“ユーザーに選ばれること”から始まる。したがって、契約を勝ち取るべく、コンペ時の提案では驚くほどの低価格を提示してくる場合がある。なかには、まともに当該提案を実行に移せば、アウトソーサーが大赤字を背負い込むのでは――と、ユーザー側がかえって心配に思うような提案をするケースもあるほどだ。だが、それは、一度契約を勝ち取れば、ユーザーが実行するほとんどの開発・保守案件を半ば自動的に受注できることを知ったうえでの戦略にすぎない。アウトソーサーにしてみれば、仮に最初の受注案件で損をしたところで、ユーザーの“アウトソーシング依存症”が重くなった時点で、サービス範囲や運用体制のあいまいさを盾に追加請求を行い、最初の損を取り戻していけば何の問題もないのである。
例えば、価格交渉の際に、「今回も、ウチの社長に泣きついて、何とかここまで勉強させてもらいました」などと、ユーザー企業に花を持たせたような言い方をするのも、アウトソーサーの得意技の1つである。実際には、そのようなケースでも、彼らにとって非常に収益性の高い案件になっているケースがかなりの割合で存在する。
また、このご時世にあってアウトソーサーも、生産性向上を図ることで懸命にコスト削減に努めており、それをコンペの際の“売り”にするところも少なくない。だが、提案書や契約書に明示されないかぎり、そうしたコスト削減への努力が料金に還元されることはほとんどない。自らの努力によって生産性向上を果たし、そのために売上げを落とすようなまねを、百戦錬磨のアウトソーサーが行うはずはないのである。
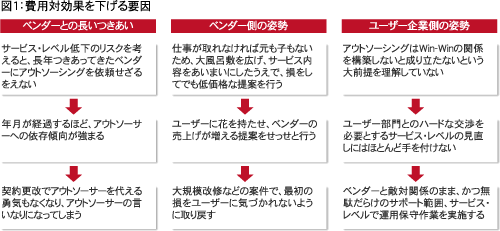
“締めつけ”より“信頼”
上のようなアウトソーサーの戦略を知れば、良い気分のするユーザーはいないだろう。だが、だからといって、ユーザーがアウトソーサーに対してあまりにも高圧的な態度を取るというのは考えものである。
現在、多くの日本企業でとられている一般的なアウトソーシングは、単に既存の組織の一部を切り出すのではなく、ユーザー企業側が組織のあり方を大々的に見直し、改革を断行したうえで、その結果、ある部分をアウトソーシング領域として切り出す――といったアプローチで進められている。
だが、どのようなアプローチを取るにせよ、ユーザー企業の組織の中からその一部分を切り出すことには違いがないわけだから、アウトソーシングを適用する領域は、ユーザー企業からすれば自らの“分身”とも言える存在であるはずだ。
“本体”と“分身”の目指すべき方向性が異なっていたり、互いが憎しみ合ったりしたのでは、組織としてうまく機能しないのは自明の理である。“本体”であるユーザー企業は、まず何よりも“分身”のことをよく理解し、なおかつ信頼して「Win-Win」の関係を構築できるよう努力しなければならないのである。こうした信頼関係に重きを置くアプローチは、前述した“丸投げ”とは根本的に異なるものである。
ところが、実際には、このことを理解していないユーザー企業が少なくない。例えば、契約時に、ユーザー側が“客”としての意識を過度に押し出し、「お前たちからサービスを買ってやるのだ。感謝しろ」というような態度をとるケースはよく見られる光景だし、アウトソーサーの戦略に乗るまいと、とにかく「買いたたく」ことを第1の目標に置くユーザー企業もある。このように、はなから「Win-Lose」の関係を目指すようなやり方はマイナスにこそなれ、プラスにはならない。
ユーザー側が強硬な態度に出れば、アウトソーサー側も当然、対抗措置を講ずる。相手が買いたたいてくるとみれば、最初の見積もりを“ふっかけ”たり、契約の中に“抜け道”を作って後々もうかるような仕組みを構築しようとしたりするだろう。そのような“かけ引き”にかけては、百戦錬磨のアウトソーサーのほうが一枚も二枚も上手だということを、ユーザーは決して忘れてはならないのである。
“サービス・レベル”の意味を知る
アウトソーシングにおいては契約内容も重要だが、サポート範囲やサービス・レベル、価格の考え方、運用体制といったことを決定するのも同様、もしくはそれ以上に重要である。
だが、多くの企業では、サービス・レベルの見直しといった、IT部門がユーザー部門や経営陣とのハードな交渉を必要とするような取り組みは敬遠されがちである。その結果、現状のサービス・レベル、現状のサポート範囲には手をつけないまま、RFP(提案依頼書)を作成しているというケースが増えることになる。
また、たとえサービス・レベル管理を実施しているにしても、「とにかくサービス・レベルを上げればよい」と勘違いしているようなユーザーも存在する。言うまでもなく、サービス・レベル管理とは、品質とコストのバランスを取るための手法である。
一方、アウトソーサーにとっては、サービス・レベルを現状より上げるということは、ハードウェアやネットワークの増強など、売上げに直結するプロジェクトの発生につながることが多いため、各社ともそれをこぞってユーザーに提案してくる傾向がある。こうした「サービス・レベル」という言葉の持つ一種の“まやかし”に、ユーザー企業は細心の注意を払う必要があろう。
また、実際のアウトソーシング契約では、「一式○○円」というきわめて大ざっぱなかたちで見積もりが提示されることが少なくない。この場合も、ユーザーはアウトソーサーに明確な説明を求めるべきである。特に、信頼関係が十分に構築されていないアウトソーサーとの契約である場合には、そうした数字を鵜呑みにするのではなく、サービス・レベルやサポート範囲を明確化するよう要請することが必須の取り組みとなろう。
昨今は、インフラのダウン・サイジングが進んだこともあり、アウトソーシング案件に占める人件費の割合が従来よりかなり高くなってきている。この人件費にも、ハードウェアやソフトウェアなどの物理的コストと同様に、無駄が多く潜んでいる可能性がある。ここでもやはり、サービス範囲をカバーするための作業内容やサービス・レベル、要員の生産性といったところにまで踏み込んだかたちで交渉を行う必要があろう。
アウトソーシング or インソーシング
実は、筆者は現在、ユーザー企業がアウトソーサーに対して支払っているコストの削減サービスを、成功報酬方式で行っている。企業から声がかかると、そのつど、依頼先のアウトソース契約を拝見し、1〜2時間ほどで検証させてもらうというものである。
そうした活動を続けてきた経験から言えば、現在、日本企業が支出しているアウトソーシング・コストは、必ずしも妥当であるとは言い難い状況にある。というのも、自社のアウトソーシング契約の内容とコストの妥当性にかなりの自信を持っているような企業でも、いざ契約内容を見ると相当の無駄を発見することができるからである。
また、ユーザー側が「何をアウトソースにし、何をインソースにするか」という明確な戦略を手にしていないケースも目に付く。
では、アウトソーシングにおける適正なコスト体系とは、アウトソースとインソースの適切なバランスとは、いったいどのようなものなのであろうか。残念ながら、この問いに対しては「会社によって異なる」と答えざるをえない。だが、以下ではあえて、CIOの方々にとって1つの判断基準になると思われる要素をいくつか紹介してみたい。
■品質とコスト・バランス
ここで言及するまでもないが、飛び抜けた品質が求められ、なおかつそれが企業のコア・コンピタンスに近い業務については、コストには少々目をつぶってでもインソースでまかなうべきである。他方、他社と変わらない程度の品質を満たせばよいという業務であれば、コスト次第でアウトソースかインソースかを決めればよいだろう。
こう書くと、きわめて単純な理屈に見えるが、現実には、この判断を的確に下せている日本企業は意外に少ない。例えば、某大手証券会社では、個々のスタッフが保有するPCのキッティングやトラブル・シューティングといったサービスを、人件費の高い正社員を使って行っていた。また、某大手銀行では、システム障害の一次受付作業を正社員によって、しかも24時間体制のシフトまで敷いて行っていた。こうした、基本スキルを持つ者ならだれにでもできるような業務をインソースでまかなうのは得策ではない。
私見を述べれば、差別化を図ってもあまり意味のない領域の業務については、コスト・カットがしやすく、かつアウトソーサーが強大な権力を持つことにもつながりにくいため、通常はアウトソーシングで安い資源を利用し、人件費の流動費化を図ることをお勧めしたい。
実際、上で挙げた2社の金融機関は、従来正社員でまかなっていた業務を部分的に切り出してアウトソーシングすることで、かなりのコスト削減を実現している。特に、銀行の一次受付のケースでは、アウトソーシングを利用することにより、それだけで年間1億円近いコスト削減を達成しているのである。
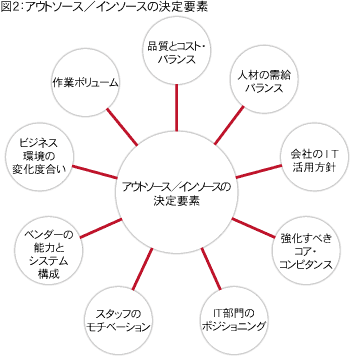
■人材の受給バランス
そのスキルを持っている要員は引く手あまた――というような業務については、アウトソーシング/インソーシングのどちらを選択するかの判断はきわめて難しい。
「そもそもそのスキルを持った要員が十分にいない」、「十分な作業量がない」、「作業量が季節などによって激変する」、「その業務がコア・コンピタンスではなく、そのスキルを持った要員のモチベーションを維持できるようなキャリア・パスが提示できない」などといった事情に当てはまる企業であれば、基本的にはアウトソーシングを考えたほうが賢明である。
だが、仮に、アウトソーサーに対する統制力を維持するのが困難であると思われるような場合には、そもそもそのようなスキルが必要とされるシステムを導入すべきなのか――というところまで立ち返って考えてみることが求められよう。
■企業のIT活用方針
ITそのものをビジネス上の戦略的な武器として活用している企業であれば、“かゆいところに素早く手が届く”ような精鋭部隊を社内に維持しておくのが望ましい。多少コストが高くついたとしても、ビジネスのシェアを高め、利益を増やすことにつながるからである。
それに対して、ITをバック・オフィス系の機能に限定しているような企業であれば、インソースではコストばかりがかさみ、それでいてITスタッフのモチベーションの維持が難しいという状況に陥りがちである。そのため、アウトソースを第1の選択肢とすべきであろう。
■ベンダーに対する統制力を手にする
程度の差こそあれ、今やほとんどの業種でIT抜きのビジネスは考えられない状況となっている。そして、このITを使いこなすためには、大まかに「IT企画力」、「ベンダー統制力」、「運用スキル」、「システム開発スキル」といったスキルが必要になる。
ほとんどの企業では前の2つ、つまり「IT企画力」と「ベンダー統制力」については社内に残し、残る「運用スキル」、「システム開発スキル」についてはアウトソーシングを適用する――という線引きを行っていることだろう。
だが、実は、これらのスキルはそう簡単に切り分けられるものではない。なかでも、「ベンダー統制力」は、ユーザー側のスタッフに一定の開発/運用スキルがあって初めて発揮されるものである。つまり、開発/運用作業をアウトソーシングしてしまうと、ベンダーに対する統制力を持ったスタッフが育成されにくくなるというジレンマがあるわけである。
アウトソーシングを利用しつつ、ベンダーへの統制力を維持するためには、高度な開発/運用スキルを持つ人材を中途採用してベンダーとの折衝役に当たらせるなどといったアプローチが考えられるが、いずれにせよ決定的な解決策はないというのが実情である。
ベンダーに対する統制力は、仮にベンダーとの関係がきわめて良好であったとしても、低下させてよいものではない。どんな作業領域であれ、統制力が落ちた時点でアウトソーシングの費用対効果が急激に低下してしまうということを覚悟すべきである。
■IT部門の存在感
企業の中には、IT部門の社内でのポジショニングが十分に確立されていないところもまま見受られる。なかには、社内のIT部門を「アウトソーサーとユーザー部門との間をつなぐ“伝書バト”」といったような存在としか見なしていない経営者もいる。
こうした見方が生まれてしまう原因は、経営陣やユーザー部門の理解不足もさることながら、IT部門のコミュニケーション能力不足にある場合が少なくない。したがって、このような企業でアウトソーシングを検討する場合、IT部門だけにディールの進行をまかせると、失敗してしまう可能性がきわめて大きくなる。「コミュニケーション能力」は、契約を進めるうえでそれだけ重要な要素なのである。
もし、不幸にして、自社のIT部門にコミュニケーション能力が不足していると感じたなら、やはり、経営層が積極的に交渉にかかわるのが望ましい。
■社員のモチベーション
システム運用作業には独自の醍醐味があり、本来であればきわめて興味深い業務である。しかしながら、ITスタッフがどうしても「企画」の面白さに目を向けたがる傾向が強いのもまた事実である。このような社員の「モチベーション」をアウトソース/インソースの1つの判断材料にするのも一案であろう。
例えば、スタッフ個々人に魅力的なキャリア・パスを提示できるなど、社員のモチベーションを高める策があるのであれば、インソースで運用業務をまかなうのもいいが、そうした対策がとれないようなら、アウトソーシングを活用したほうが、業務効率が上がる場合が少なくない。
また、自社のITスタッフをアウトソーサーに転籍させたうえで、そこからサービスの提供を受ける――というような手法をとる企業がここにきて増えているが、その場合も、スタッフのモチベーションがアウトソーシングの成否を大きく左右すると考えられる。
そうしたケースでは大抵の場合、すでにブランドが確立されている大企業が受け入れ先となるものだが、逆にあまり知られていないような企業が受け入れ先となる場合には、スタッフの拒否反応が強くなり、転籍先で業務に対するモチベーションが上がりにくくなる可能性がある。それでは、何のためにわざわざアウトソーシングを行うのか分からない。転籍を伴う場合は、受け入れ先企業のブランドも考慮に入れるべきである。
■ベンダーの能力とシステム構成
アウトソーシングを行う場合に、ユーザー企業がつきあいを重視する傾向にあるということはすでに述べたが、いくらつきあいがあるとはいっても、そのベンダーの能力を正しく評価していなければ、アウトソーシングの継続的な成功は望めない。
アウトソーサーとしての機能を持つベンダーは現在、数多く存在するが、それぞれに「強み」、「弱み」を持っている。例えば、汎用機に関するスキルは一流だが、Web系システムや最新テクノロジーに関連するスキルには不安を持つといったような、スキルに偏りがあるベンダーもある。そうしたベンダーと長期的な関係を結んでいたのでは、自らのITリソースの拡張性が失われてしまうおそれがある。
基本的には、今後のIT環境の変化に備え、“アメーバ的”なアウトソーシングを実行できるようなスキームの下で契約を検討することをお勧めしたい。
■ビジネス環境全体の変化
現在、システム環境のみならず、あらゆる業種でビジネスを取り巻く環境自体が大きく変化している。このように、ビジネス環境が急速に変化しており、なおかつその変化が今後もしばらくは続くであろうと見られる場合には、一般的にアウトソーシングの領域を狭めたほうが賢明であることが多い。
というのも、システムの大規模改修や新規構築などの案件に対応するには、自社のシステムだけでなく自社のビジネスをもきちんと理解した人材が不可欠だからである。このスキルをアウトソーサーに求めるのは、無理な注文であろう。
確かに、システム面でのスキルは、アウトソーサーでも補うことが可能かもしれない。だが、システムのスキルを備えたうえで自社のビジネスを深く理解している人物ということになると、やはり社内スタッフに一日の長がある。
以上の点から、ビジネス環境の変化度合いが激しい企業ほど、アウトソーシングのメリットが薄れ、逆にインソーシングのメリットが増すと考えてよいだろう。
■作業ボリューム
さまざまなアプリケーション機能を持つERP(Enterprise Resource Planning)システムを運用するような場合には、すべての機能をカバーする必要があるため複数のスタッフをそろえることが求められる。しかし、こうした手法をとった場合、各機能の作業ボリュームが1人分に満たず、結局スタッフの経費が無駄になってしまうケースは珍しくない。
有事に備えて必要な頭数を確保しておく重要性も分からないではないが、余分な人件費はなるべくカットしたいというのが企業の本音だろう。そういった場合にこそ、絶大な効果をもたらすのがアウトソーシングである。
ここでは、最近日本でも導入例が増えているAMO(Application Management Outsourcing)の活用が検討すべき選択肢ということになる(本誌2003年3月号 78ページ参照)
あるべきアウトソーシングの姿
ビジネス環境の激変、求められるITスキルの進展と多様化――これらは今や世界的な大潮流であり、だれにも止めることはできない。こうした中である程度の規模の企業が生き残っていくためには、やはりすべてのIT業務を自前でまかなうのは不可能であり、ゆえにアウトソーシングは避けて通れない取り組みということになる。
ただし、商品のライフサイクルはもとより、ビジネスのライフサイクルも急速に短命化している現在では、まるで“運命共同体”のごとく、特定のアウトソーサーとあいまいな内容の長期契約を結ぶという従来型の契約方法では、ビジネスにおいて機動力を損なう結果になりかねない。
であるならば、今の激動の時代に適したアウトソーシングを実行するために、ユーザー企業は何をなすべきなのであろうか。結局は初心に帰り、アウトソースとインソースの適正バランスを見極めつつ、アウトソーシング・コストの妥当性を乱している要素を1つ1つつぶしていくというような地道なアプローチをとるしかないというのが、筆者の考えである。
しかし、「言うは易し、行うは難し」である。以下、CIOが今すぐに実行に移すことができると考えられる取り組みをいくつか紹介して、本稿の締めとさせていただきたい。
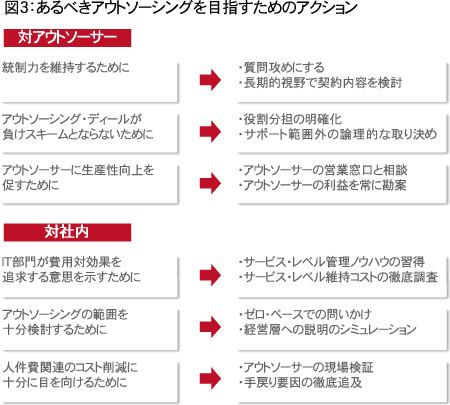
【対アウトソーサー】
すでに、アウトソーサーに対する統制が不足してしまっていると感じられるのであれば、とにかく分からないことは納得のいくまでアウトソーサーに尋ねてみることだ。そうすることで、知識の差を徐々に埋めることも可能になる。
しかしながら、アウトソーシング契約を検討する時点で、長期的に統制力が維持できるか否かを見極めることが、何よりも重要であることは言うまでもない。
また、ユーザーとアウトソーサーの「共同作業」をできるだけ排し、必ずどちらかの責任となるよう、作業内容を詳細に定義したり、作業範囲をオーバーした場合の取り扱いを「両社協議のうえで決定する」といったようなあいまいな記述ではなく、どのようなロジックで決定するかをあらかじめ明確化したりすることも大事だ。こうしたことが、ひいては価格面での不透明さを排すことにつながるのである。
また、アウトソーサーと「Win-Win」の関係を築くにあたっては、ユーザーが自らの利益のみならず、アウトソーサーの利益をも意識して交渉に臨むことが大切である。
【対社内】
アウトソーシングの問題を、社内の経営陣やユーザー部門の視点で考えれば、IT部門に求められるのはやはりアカウンタビリティ(説明責任)ということになる。IT部門自身の考えをまずは社内に広く示し、支持を取り付けることから始めていただきたい。
IT部門がユーザー部門と戦ってまで費用対効果を追求するという意思を示すためには、CIOならびにITスタッフが、サービス・レベル管理についてのノウハウや成功事例を自らの言葉として話せるまでに習得しておくことが不可欠である。
また、アウトソーシングする作業範囲の検討にあたっても、「なぜインソースに適さないのか」、「バランスは適正なのか」というポイントでそれぞれを評価したうえで、経営陣、ユーザー部門に説明できるようにしておきたい。
結局のところ、その手法がアウトソーシングであれ、インソーシングであれ、本来はどうすればITリソースの効果を最大限に発揮させ、競争優位を確保できるかということが最大の命題であるはずである。CIOが自社のITリソースをどう位置づけ、それを運用するにあたってどれだけ明確なビジョンと戦略を打ち立てることができるか――アウトソーシングの成否を握るカギはここに集約されるのである。


