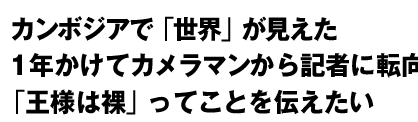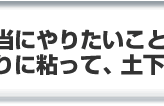|
同じ報道写真を撮るのでも、媒体、会社によって全然違うから、まずは「新聞社のカメラマン」という仕事に慣れるのに必死だった。仕事の内容の他に、社風とかもあるからね。でも先輩や上司に「こうしろ」って言われても、自分が「それは違うんじゃないか」って思ったら従わずに、自分のやり方で撮ってたな。
あとがむしゃらに働いてたのは、離婚をしたせいでもあったんだけどね。あのころは金もなかったし、精神的にも仕事に打ち込むしかなかったから……。写真だけじゃなく簡単な記事も書いてたんだよ。表現者として記事を書きたいと思ったんじゃなくて、書くと取材費で食事代を浮かせることができたから。ただそれだけ。
でもオレは自分のために仕事に没頭してたんだけど、それが会社には認められて、ご褒美で東欧取材に行かせてもらえることになった。日曜版の「世界のマーケット」っていう、世界の市場を紹介する企画の取材だったんだけど、ちょうどそのころベルリンの壁が崩壊寸前で、東ベルリンから市民が逃げ出したりし始めたころでさ。おもしろいからそっちも撮って本社に送ったら「あいつは市場の取材で行ってるのに、ニュースを撮ってきた」ってみんなびっくりしてさ。それがきっかけとなってその後湾岸戦争とかアフガン、イラク、ルワンダとかの紛争取材に呼ばれるようになったんだ。
オレ自身も戦場取材は好きだったんだよね。普通に暮らしてたら絶対に味わえない、非日常の最たる世界だから、やればやるほどおもしろくなってくる。どんどん刺激が欲しくなって危ないところへ行きたくなるんだ。危険であればあるほど生の充実感を得られるっていうのかな。だから何度か死にそうなメにあったよ。
湾岸戦争ではオレめがけて降ってきたスカッドミサイルをパトリオット迎撃ミサイルが目の前で撃墜した、なんてこともあった。そのときはさすがに冷や汗をかいたけど、「目撃した!」という興奮と喜びを感じたよね。
だから少なくともオレは使命感を持って戦争取材をしてたんじゃない。オレ自身がもっと刺激的なものを見たいから行ってたんだな。それは人間の生理だと思うよ。
そういう写真を撮ってたら朝日新聞からウチにこないかって話が来てさ。朝日の編集委員が2人がかりでオレを引き抜こうとしたんだよ。39歳ころだったかな。もし転職すると給料が1.5倍くらい上がるから一度は乗り気になったよ。その頃高いマンション買ってとにかく金がなかったからさ。だけど、朝日の現場のカメラマンたちがNOって言ったらしいんだ。「歳を食いすぎてるから使いづらい」って(笑)。
|


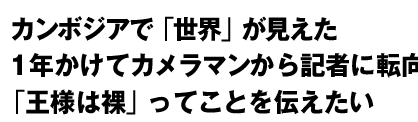




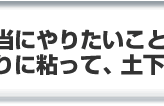


 転職研究室
転職研究室
 魂の仕事人
魂の仕事人
 第6回新聞記者・作家 吉岡逸夫さん-その3-カンボジアで「世界」が見えた
第6回新聞記者・作家 吉岡逸夫さん-その3-カンボジアで「世界」が見えた